睡眠
健康と睡眠
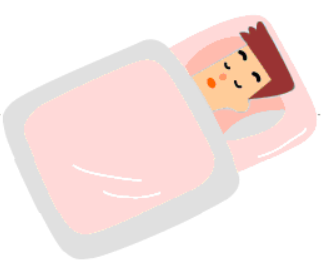
睡眠不足を含めた様々な睡眠の問題が長引くと、肥満や高血圧、糖尿病、心疾患や脳血管障害の発症リスクの上昇や症状の悪化などを引き起こすことが明らかになってきました。
最も身近な生活習慣である睡眠を見直し、ぐっすり睡眠Good Sleepを目指してみませんか。
●健康づくりに大切な睡眠のポイントは2つ!「量」と「質」
睡眠時間の確保(量)と睡眠休養感(質…睡眠で休養がとれている感覚)です。
●成人の睡眠時間の目安は「6時間以上」
仕事、家事などと忙しい生活を送っていると、慢性的な寝不足になりがちです。
6時間以上の睡眠を確保できるように、日々のスケジュールを工夫しましょう。
1.生活習慣
・運動を習慣化しましょう
適度な運動習慣を身につけ、日中にしっかり体を動かすと、寝つきがよくなる等、睡眠の質が高まります。
朝食を摂取すると、体内時計が調整され、睡眠、覚醒のリズムが整います。
・寝る直前の夜食や間食を控えましょう
寝る直前の夜食や間食は、体内時計を後退させ、翌朝の睡眠休養感の低下等をまねきます。
・減塩を心がけましょう
食塩を過剰に摂取すると、睡眠中に排泄しようと夜間の排尿回数が増加することが、報告されています。
2.嗜好品
・カフェインは1日400mgを超えないようにしましょう
カフェインは覚醒作用があります。
コーヒーであれば、1日700cc程度(カフェイン400mg)にしましょう。
下表の他、エナジードリンクにも含まれています。
特に夕方以降のカフェインの摂取は、寝つきを悪くする、眠りが浅くなるなどの影響があります。
| 玉露 | 160mg |
| 紅茶 | 30mg |
| せん茶 | 20mg |
・晩酌は控えめにして、寝酒は控えましょう
アルコールは寝つきを促す一方で、体内の代謝過程で、興奮性のある物質が産生されるため、夜中に何度も目が覚める中途覚醒が生じます。
・良い睡眠のために、禁煙を目指しましょう
たばこに含まれるニコチンは、寝つきを悪くし、また中途覚醒を増加させ、深い眠りの時間を短くします。
3.環境づくり
・朝日を浴びましょう、日中に光を多く浴びましょう
体内時計がリセットされ、睡眠・覚醒リズムが整い、良い睡眠に繋がります。
・できるだけ寝室は暗くしましょう
寝ている間は、低い照度の光でも、中途覚醒を増やすことが報告されています。
・寝室にスマートフォンやタブレット端末を持ち込まないようにしましょう
スマートフォンやタブレットには、体内時計に影響を及ぼすブルーライトが含まれており、寝つきに影響を及ぼします。
・寝る1時間前は家事や仕事から離れリラックスしましょう
入眠をスムーズにするためには、家事、仕事、勉強などに追われずにリラックスし、脳の興奮を鎮めることが大切です。
時間をとっても眠い、睡眠時間の確保が生活上難しい、など個人差もあるかと思います。
できる取り組みから始めてみましょう。
睡眠習慣を改善しても、眠りの問題が続く場合は、医療機関に相談しましょう。
参考(高齢者、子どもの睡眠に関する情報も個別あります。)
厚生労働省ホームページ 睡眠対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/suimin/index.html
眠れないが続いたら…

1.不眠とうつ
2週間以上続く不眠は、うつ病のサインかもしれ
ません。眠れないときは、医師等に相談を。
疲れているのに眠れない…そんな状態が2週間以上
続いていたら、うつ病のサインかもしれません。
うつ病はだれでもかかる可能性がある病気です。
そして、自殺とも深いつながりがあるといわれます。
眠れない、疲れやすいなどからだの不調に気づいたら、
一人で悩まず、放っておかずに早めに医師に
相談してください。
●「うつ病」はだれでもなりうる身近な病気
朝、目覚ましよりも早く起きてしまう。疲れがとれず、からだがだるい。日中、強い眠気を感じる。やる気が起こらず、集中できない。イライラする。肩こりや頭痛がする。疲れやすい。食欲もなくなった。悲観的な考えが浮かぶ。テレビを見てもつまらない。夜、ふとんに入ってもなかなか眠りにつけない…。これらは、「単なる疲れ」と見過ごされがちですが、うつ病によく見られる症状です。うつ病は特別な病気ではありません。心配や過労・ストレスが続いたり、孤独や孤立感が強くなったり、将来への希望が見出せないと感じたりしたときなど、だれもがかかる可能性のある病気です。厚生労働省の調査によれば、うつ病にかかる人は日本人の15人に1人となっており、特に、几帳面で真面目、責任感が強い人がうつ病になりやすいという傾向があります。
厚生労働省「知ることからはじめよう みんなのメンタルヘルス「うつ病」」
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_depressive.html
●悪化すると自殺につながるケースも
うつ病が進んでいくと、自分に価値がないと感じたり、罪の意識を感じるなどのつらい思いをし、自殺を考えるようになります。実は、うつ病と自殺は密接な関係があり、WHOによると、自殺した人の約9割は、うつ病などの精神疾患を発症しているとされています。
内閣府発表の地域における自殺の基礎資料によると、日本では平成10年から自殺者数が年間3万人を超えて推移していましたが、平成24年に15年ぶりに3万人を下回り、平成26年は2万5,427人でした。
年齢階級別の自殺者数の推移は、75歳以上を除いて、減少傾向です。
さいたま市における平成26年の自殺者数は208人で、自殺死亡率(人口10万人あたりの自殺者数)は全国や埼玉県と比べると若干ではありますが低い状況が続いています。
自殺者数の男女別構成割合は、男性が全体の70.2%と高い状況です。
年齢階級別構成割合は、40歳代が全体の20.3%、30歳代が16.9%と働き盛りの世代が高い結果でした。
20歳未満は5.3%と全体に占める割合は高くなかったものの、自殺者数の推移は増加傾向です。
厚生労働省「こころもメンテしよう~若者を支えるメンタルヘルスサイト~「うつ病」」
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/stress/know/know_01.html
2.うつ病のサインに気づき、早期治療につなげる
うつ病による苦しみや自殺をなくすためには、うつ病を早期に発見し、専門家の治療につなげることが重要です。うつ病の初期段階では、眠れない、食欲がない、からだがだるいといった、具体的なからだの不調が現れます。自分や周囲の人にそうしたからだの不調が続いていないか、気づくことがうつ病の早期発見につながります。人によって現れる症状はさまざまですが、その中でも、うつ病に特徴的なのが「眠れない」などの不眠の症状です。
寝つきが悪い、夜中に目が覚めてしまう、早朝に目が覚めるなど、不眠が2週間以上続く場合は、うつ病のサインかもしれません。不眠は放っておくと、日常生活や仕事などにも支障を来し、うつ病をさらに進行させることにつながります。うつ病は、早期発見・早期治療が重要です。そのため、2週間以上続く不眠に気づいたら、早めに医師や専門家に相談することが大事です。うつ病は本人が気づかないことも多いため、家族や職場の同僚など周囲の人が気づくことも重要です。
●うつ病のサイン
| 本人が気づく変化 | 周囲の人が気づく変化 |
|---|---|
| 1.悲しい、憂うつな気分、沈んだ気分 2.何事にも興味がわかず、楽しくない 3.疲れやすく、元気がない(だるい) 4.気力、意欲、集中力の低下を自覚する(おっくう) 5.寝つきが悪くて、朝早く目がさめる 6.食欲がなくなる 7.人に会いたくなくなる 8.夕方より朝方の方が気分、体調が悪い 9.心配事が頭から離れず、考えが堂々めぐりする 10.失敗や悲しみ、失望から立ち直れない 11.自分を責め、自分は価値がないと感じる など |
1.以前と比べて表情が暗く、元気がない 2.体調不良の訴え(身体の痛みや倦怠感)が多くなる 3.仕事や家事の能率が低下、ミスが増える 4.周囲との交流を避けるようになる 5.遅刻、早退、欠勤(欠席)が増加する 6.趣味やスポーツ、外出をしなくなる 7.飲酒量が増える など |
●あなたの「こころ」…だいじょうぶ?
ここ2週間ほど、こんな状態が続いていませんか?チェックしてみましょう。
<こころの健康度チェック>
□ 毎日の生活に充実感がない
□ これまで楽しんでやれていたことが、楽しめなくなった
□ 以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられる
□ 自分が役に立つ人間だと思えない
□ わけもなく疲れたような感じがする
↓
2つ以上があてはまりそのためにつらい気持ちになったり、毎日の生活に支障がある人はうつ状態の可能性があります。
(平成16年1月「うつ対策推進方策マニュアル厚生労働省地域におけるうつ対策検討会より」)
市内のこころの健康相談窓口は下記をご覧ください。
さいたま市「「こころの健康ガイド ~ひとりで悩んでいませんか~」を配付しています」
(下記リンク先の「相談窓口」をご覧ください。)
https://www.city.saitama.jp/002/001/016/004/p013023.html